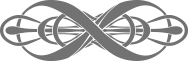NOVEL
「終わった」と思った瞬間に、‘それ’は始まった
気づいた時が始まりなのか?
気づいた時はもう遅いのか?
――暗闇と静寂の
「52Hz」
Introduction
―Fate steps in without notice―
――カッ。
少女の足音が暗闇の中に響いた。
黒い空に浮かぶ下弦の月は、西に向かいながらやんわりと光を放ち、少女のたよりない背中を照らしていた。
目前に広がる黒の世界。静寂。
鉄筋コンクリートを踏み締める少女の目が、意を決したような、それでいて何処か虚ろな色を帯びていたのは、欠けていく月のように彼女の心もまた、何かが満ち足りていなかったからかもしれない。
もうすぐ初夏だというのに、少女の短い栗色の髪を撫でる風はまだ冷たかった。
――疲れた……
この世界はいつだってそう。
「真実」なんてドコにも無い。
表面に繕われた都合のいい言葉。その場限りの絆。早送りのように入れ替わる情報。気を抜いたら付いていけなくなる。用済み。シカト。ハブられた。
誰も自分を必要となんかしていない。
混沌の中、ただ繰り返しの日々を送るだけ。
こんな世界で生きる意味。生きていてもいい意味。
……そんなものあるの?
ちっぽけな存在。
どこかで私が泣いていても、きっと誰も気付かない。
偽りの優しさにも、平気なふりして笑う自分にも……もう疲れた。
もう十分だ。これ以上知りたくない。知ってもがっかりするのはもうわかってる。人にも自分にも、この世の中にも何もかも――
さようなら。世界。
私はもう、終わりにする。
少女は、空に向けて一歩踏み出す。
不意に、ポケットの中の携帯電話が震えた。
「…………」
少女は携帯電話の通知を開き、画面を確認する。
そして。
ふうと小さく息を吐くと、するりと携帯を放った。
少女はその華奢な身体を、黒い空の中へ
この世界との決別だ。
やっと。
ようやく、終わらせることが出来るのだ。
安心し、身を任せる鳥のように、空の中に沈んでいく。
この身体が再び地面に着く頃には、きっと全てが終わっているだろう。
全ての苦しみから解放され、残酷な日常ともおさらばだ。うんざりしていた日々にようやく終止符を打つことが出来るのだ。
そう、全てが終わる……
はずだった――
「な、何っ……!?」
突然、どこからともなく黒煙のような風が湧き
吹き荒ぶ風の騒音と共に、ものすごい勢いで、一瞬にして全身を覆われる。
「……っ!?」
手足が動かない。首も固まったままだ。
黒い霧の中で自分が今、上を向いているのか逆さになっているのかさえもわからなかった。まるで無重力状態――
「……ハっ……!」
息が鼻を抜けた。
声を発することも出来ないのだ。
というより、風圧が強すぎて呼吸さえままならない。苦しい。
さっきまで死のうとしていた人間が、遠退く意識の中でそんなことを思い浮かべるなんてどうかしているかもしれない。
どんどん霞に包まれる。
どんどん闇に飲み込まれていく。
何も見えない。ゴオゴオと耳に入ってきた風の音さえ止んでいく。
おぼろげな意識も心地良いくらい真っ白になっていき、いつしか全ての感覚を失った……。
それはほんの僅か、一瞬の出来事だった。
およそ見物人などがいたら、幻覚だと思うような情景だっただろう。
夜更けのマンションの屋上から飛び降りた少女は、漆黒の風と共にその姿を消してしまった。
***
「え……?」
次の瞬間、少女の意識はマンションの前の道路に立っている自分を確認した。
何の変哲もない。いつものように制服を着て、いつものように出掛けて……
――
いつも、自分は、何をしていた?
さっきまで、自分は……何をしようとしていた?
「…………」
覚えていない。思い出せない。
自分はどこに向かってこの道を歩いていて、何をするつもりだったのか。
そもそも今日が何月何日で、今が何時なのかもわからない。
辺りがうっすら暗いことから、夜だということだけはわかるが、これが夕暮れ時なのか朝が近いのかまでは判断出来ない。
「私、どうしちゃったんだろう……」
狐につままれたような思いでひとつひとつ記憶を手繰り寄せてはみるものの、いっこうに戻ってくる気配がない。
それ以前に自分は、いったい誰なのだろうか……?
何もかもがよくわからない。
呆然と突っ立っていた辺りを思い出したように見回してみると、どことなく見覚えのあるマンションに、閑散とした公園、少し先にはコンビニがあるのがわかった。
この景色、知っている。
何故だかそう思えた。
――だけど。
公園て、こんなに大きかったっけ?
この静かな公園は、もっと小さくて、遊具など一つ二つくらいしかなかったような気がするのだ。
「何これ……? 意味わかんない……」
こんな、今がいつで、何処なのかもわからない場所で、自分が誰かさえもわからずに、これから一体どこへ向かえばいいのか、何をすればいいのか……途方に暮れるばかりだった。
「すみません」
そんな時、人気のなかったはずの背後から突然声を掛けられた。
驚いて振り返ってみると、
「驚かせてしまいましたか。申し訳ございません」
ジェントルマンさながらのかしこまった雰囲気に、少女はかえって恐縮してしまう。
「あ、いえ……」
ぺこりと頭を下げながら、よく見てみると後ろにもう一人、女の子が立っているのに気が付いた。
自分と同じくらいの年頃だろうか? 長い艶やかな黒髪の少女が、グレーのパーカーのポケットに手を突っ込んで、キリリとした切れ長の――深い海のような冷静な目でこちらを見ていた。
「ああ、彼女は――」
少女の視線に気付いた眼鏡の男が、黒髪少女に向き直る。
すると、じっと立ち止まって見ていた足が一歩こちらに近付き、パーカーのポケットから手を出すと、口元を覆っていたブルーのネックウォーマーをくいと摘んで
「……この辺?」
と、少女の存在を確かめるように眼鏡の男に問い掛けた。
「ええ」
――この辺……?
黒髪少女の投げ掛けた不自然な質問に、少女は首を傾げた。
「……ここに、いるのね?」
「いますよ、アイ」
――アイ……?
「……っ
黒髪少女――アイという名前を聞いた途端、一瞬だが頭にズキリと痛みが走った。少女は額を抑えて俯く。
「大丈夫ですか?」
男がすかさず手を差し伸べてくれる。
が、少女は手を取らずに「平気です」と遠慮した。ほとんど本能だった。他者との距離を保たねばならないような気がしたのだ。
「そうですか。それならいいですが……無理はしないでくださいね? わたくし、申し遅れましたが――」
黒縁眼鏡を再びくいっと押しやって、男がこちらに改まる。
「私の名前は、ディーといいます、そして彼女がアイ」
――ズキリ。
まただ。
この黒髪少女の名前が呼ばれる度に、頭がズキズキと痛むのだ。
「本当に、大丈夫ですか?」
と、心配そうなディーと、不思議そうな顔で
「どうしたの? ヤバイの?」
「いえ……」
アイの声色はクールだった。端正に整った顔立ちに、イメージ通りの涼しい声。美人だけど、歳も近そうだけど、妙に落ち着いている。そんな印象を少女は受けた。
――だけど、なんだろう……。
どうして彼女は、私と目を合わせないのだろう?
私が……見えてないの?
「だ、大丈夫、です」
少女は額を押さえながらも、顔を上げてディーに向き直った。
「…………わかりました……では、続けましょう。あなたは、自分の名前を覚えていますか?」
「そ、それが――」
覚えていない、と言おうとして言葉を紡ぎかけたその瞬間だった。
少女の脳裏に突然、「A」というアルファベットが浮かび上がってきた。
強い呼び掛けで、アニメの映像みたいに頭の中を行き来する。
――A、A、A、A、A!!
「A」のアルファベットだけが、やたらと頭の中に響き渡る。
脳裏にあるはずの「A」という文字が、すぐ目の前に見えてきて掴めそうなくらいの強烈な印象を植え付けてくる。
まるで、それが自分の名前の一部であるかのように。
――そう名乗れと、言わんばかりに……。
脳裏に刻まれた「A」の文字。
――これはいったい何……。幻覚? 幻?? それとも私、夢でも見ているの……?? 意味わかんない。キモチワルイ。
「どうしました?」
「…………」
どう返したらいいのかわからない。まさか自分の頭の中に文字が浮かんで語りかけてくるなんて有り得ない話、初対面の人間に言えるはずもなかった。
何も言えないでいると、ディーが気遣わしげにこちらを見て、
「顔色が優れませんね。――アイ、ちょっといいですか?」
――また黒髪少女がアイと呼ばれたその拍子だった。
何かが弾けたように少女の頭の中で「A」の文字と「アイ」の音が、綺麗に重なった。
――そう、か……
途端、頭の中のモヤモヤが晴れてくる。
――そうだ
引っ掛かっていた何かが、ピッタリとはまる。
――そうだった……私は…………
違和感の正体は、‘これ’だったんだ。
――私の名前…………私の名前は……
ふと、少女のポケットから携帯電話がすべり落ちた。
少女は携帯電話を拾い、画面を見つめる。
「……………………」
少しの間があった。
そして今度こそ少女は、ハッキリと言葉を口にした。
「私の名前は……あい」
――その時だった。
少女が自分の名前を口にしたその瞬間、再びすごい勢いで黒い疾風が巻き起こったのだ。
「――なっ!!」
助けを請うのはおろか、叫ぶ間も、もちろん別れを言う間もない。
黒い霧は、またもその華奢な身体をあっという間にすっぽり覆い込んでしまった。
二人が何かを言っているように見えたけど、それどころではなかった。
手足の感覚がなくなる。
口もきけなくなる。次は耳。
そうよ。さっきもこうやって、私はここに来たのよ。
またこの風に包まれたってことは、きっと自分の世界に戻るのね。
だけどあれ……?
私、あっちの世界で、何してた――?
闇は、少女の記憶も感覚も、全てを奪ってまた‘元の場所’に運んだ。
再び少女が意識を取り戻したのは、あのマンションから飛び降りた瞬間の――つまりは黒い空の中……。
「……私、は…………」
うっすらと目を開ける。意識はハッキリしなかった。夢から醒めてまだ間もない瞬間のような感覚だ。
――あれ? 私、さっきまで、どこか別のところに居て……誰かと何か話していたような気がするケド……。
けれど……。
それが、どこだったのか?
誰と何を話していたのか?
そんな記憶が還ってくることはなかった。
地上が近付いてくる。
張り巡らせた記憶を辿っても、答えを得る間もなく――
目の前は、真っ黒になった……